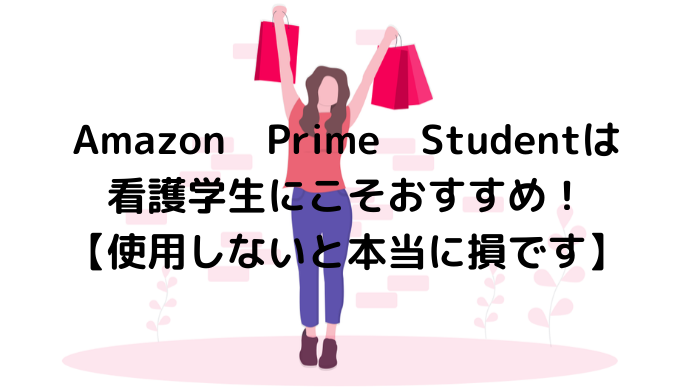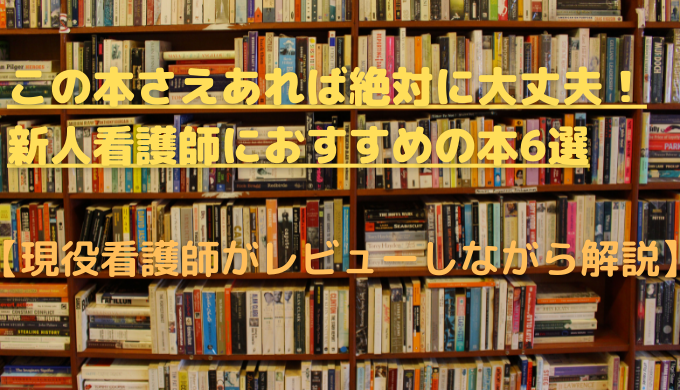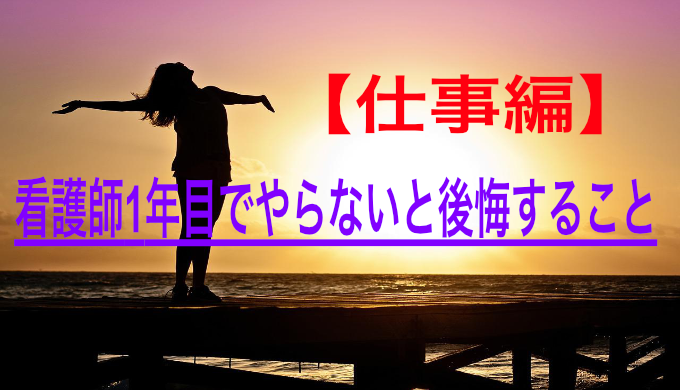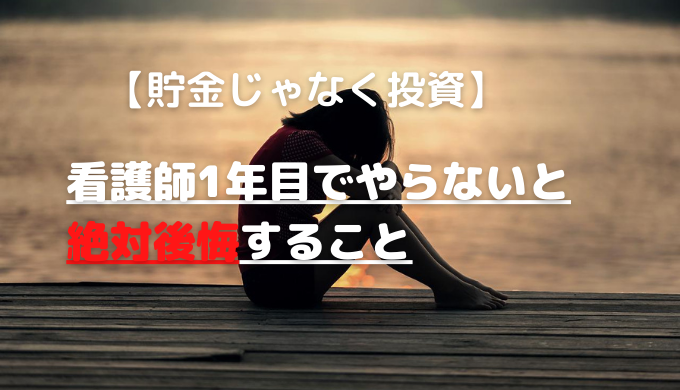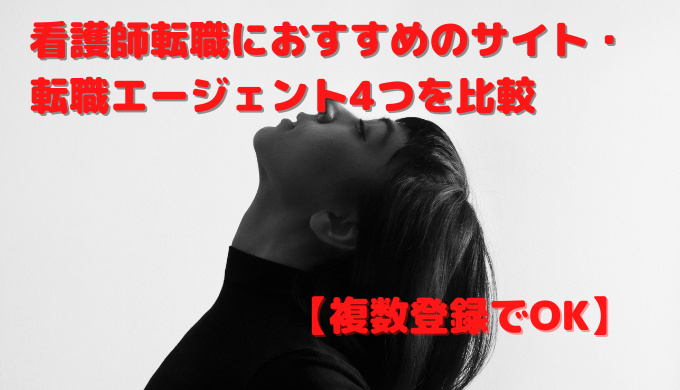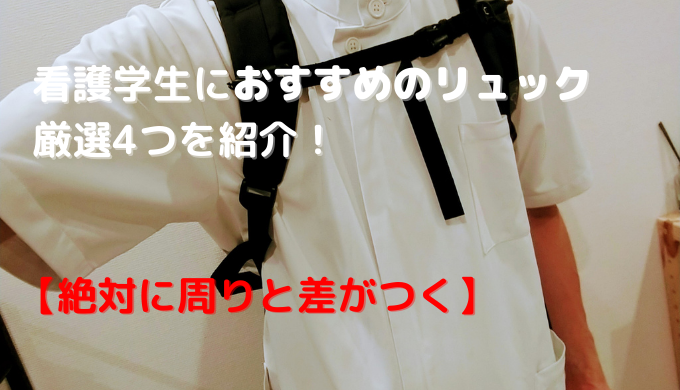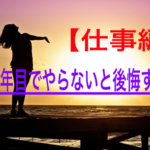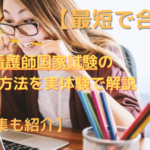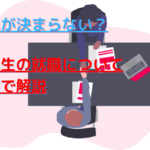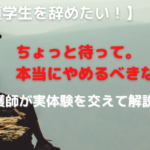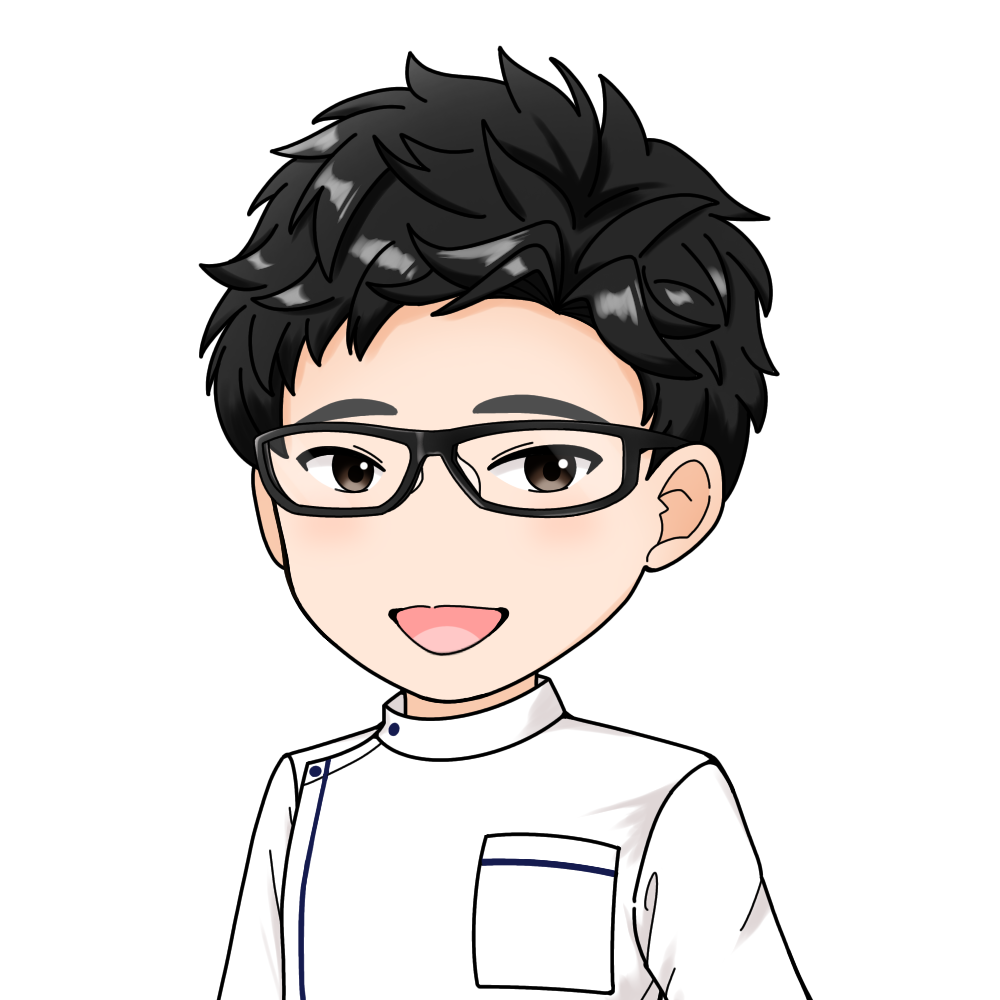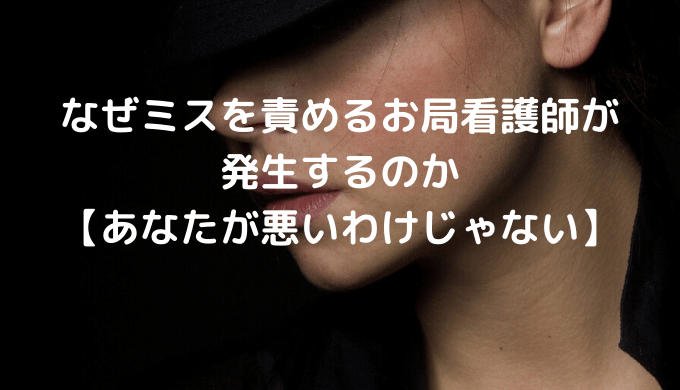
看護業界ではすっかりおなじみとなった【お局】という言葉。あなたは知っていますか?
もちろん知ってますよね。というか職場に沢山いるのではないでしょうか。
正確な定義はありませんが、「中年独身の口うるさい女性の上司」といった意味合いで、使われることが多いと思われます。新人看護師に最初に立ちはだかる壁ですね。
もちろん、新人のことを思ってアドバイスするのはお局ではありませんよ。それは良い上司です。
お局は、感情を載せて怒鳴ったり、ミスを探すような行動をしてくる人たちのことを指します。
一般的に考えると、新人が育つことは中年層にとってとてもありがたいことです。仕事の指示ができるし、自分の仕事が減りますからね。新人が仕事ができないのは当たり前です。まして看護師は仕事を覚えるだけでなく、疾患に関する勉強も必要です。大変なのは当然なんですよね。
しかし、それでもお局は新人をいじり倒します。まるで、他にすることがないように…。
このようになってしまうのはどうしてなのでしょうか。
✔記事の信頼性
・精神科看護師
・スーパー救急病棟勤務
・プリセプター経験あり
今回はお局のような、「自分は手を抜いて新人をいじめだす存在」がなぜ発生するのか。
「社会的手抜き」といわれる心理を用いて解説していきます。
目次
社会的手抜きとは

社会的手抜きとは、「集団で仕事をする方が1人でする時より、1人当たりのパフォーマンスが低下する」現象のことです。
病棟は看護師が数十人いて成り立ちますよね。そして看護師は1人では仕事をすることができません。
仮に、看護師の成果を「当初の予定通り退院ができた」とします。病棟では、患者の回転数が重要になりますね。しかし、集団で退院を目指すとどうしても手抜きをする看護師が表れてしまうのです。
詳しく解説します。
リンゲルマン効果
社会的手抜きを実験で最初に明らかにしたのはリンゲルマンです。
「集団全体のアウトプットが個人からのインプットを加算したものよりも少なくなること」をリンゲルマン効果といいます。
彼はこのような実験を行いました。
実験の内容
9名の実験参加者を用意。
9つのブースを用意し、ブースにはそれぞれ天井からロープがぶら下がっており個人の腕力を同時に測定できるようになっている。
実験参加者には「集団作業の実験であり、ここでは数人の人がいっせいに力を入れた場合、全体でどれくらいの力を出すのかを調べている。」と説明。
もちろん個人の力が測定されているがその事実は伏せる。
この実験では最初に単独の力を測定、その後集団で10回行い、最後にもう一度単独で試行した。
結果は驚愕の内容となりました。
男性も女性も単独の場合に比べて、集団でおこなったときの方が明らかに力が低下していたのです。
すなわち、集団が増えるほど、人は手抜きをしていくということが分かります。
この実験から「集団サイズが多きいほど集団全体のアウトプットと個人のアウトプットの合計の差が拡大する。」ことをリンゲルマン効果と名付けました。
なぜこうなってしまうのでしょうか。簡単に解説していきます。
社会的手抜きが発生する要因

社会的手抜きはどうして発生してしまうのでしょうか。どうやらいくつかの要因があるようです。
評価可能性
人間は集団に対する貢献度が自分や他人に分かる「評価可能性」に影響されています。
例えば、
自分の実績が明らかに数値になって、目に見えてわかる営業マンは「評価可能性」が高い。
逆に、数値が見えにくく評価のしにくい看護師は「評価可能性」が低い。
看護師の評価はどうしても上層部に依存します。自分の評価が不透明であるほど、やる気がそがれていってしまうのです。
お局だって最初はやる気に満ちていた時代があるはずです。
それが「評価可能性」が低いことにより、徐々にモチベーションが落ちていき、手抜きをしてしまうのだと予測できます。
評価可能性が低いために、社会的手抜きが生じてしまうのです。
努力の不要性
自分の努力が集団全体の結果にほとんど影響しないことを「努力の不要性」といいます。
例えば、プロ野球選手は、一人ひとりのパフォーマンスがそのまま結果に直結。年収に反映されますよね。
看護師はチームであり組織なので、努力の結果がそのまま成果につながります。ただし、1人1人の数字は不明瞭であり分かりづらいです。
日々の仕事に集中すると、成果を意識するのが難しくなります。
上司が「インシデントの数、入院受入数、退院数」これらを看護師1人1人に示し、労をねぎらう必要があるでしょう。
手抜きの同調
自分がするべき仕事をしなくても、集団全員に平等の報酬が与えられるのであれば、だれしもただ乗り(free ride)をする傾向があります。
自分が一生懸命に頑張っているのに、他人が全力を尽くしていないときに、それがばかばかしいと感じることはありませんか?KAIはよくあります。
新人看護師が必死に業務をしているときに、NSステーションでおしゃべりをするお局なんか典型的ですよね。
看護師は経験年数で給料が決まるという古いシステムを採用しています。頑張っている自分と、手を抜いても給料の高いお局。
やる気をなくしていくのは当然ですよね。そうやって誰かが手抜きをすると、みんなが手抜きをし始めます。手抜きの同調です。
お局はお局を見て、手抜きを始めた悲しき人たちなのです…。
ただ乗り、集団に貢献することなく手段から利益のみを得るような行動全般を指す
緊張感の低下
誰しも仕事を継続していると、業務に慣れてきます。新人看護師の頃は恐る恐るやっていた手技も、慣れてくると体が覚えているので、緊張が少なくなります。
このように緊張感がなくなると、人は手抜きを始めます。
KAIも昔に比べて緊張感は減りましたね。緊張が減った分、他の業務に集中する力を割くことができるので、成長のためには仕方がないことだと思います。
こうしてお局が発生する
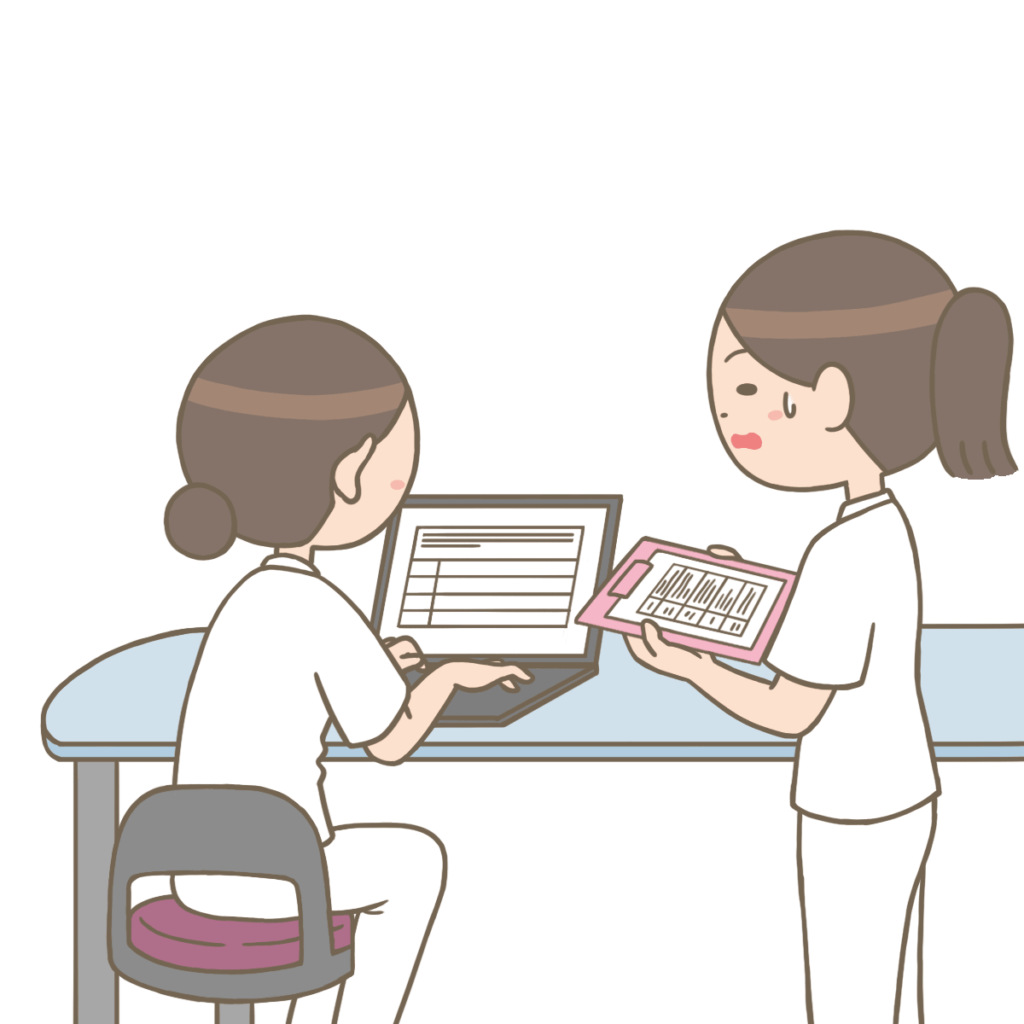
このように「評価可能性」の低さ、「努力の不要性」、「手抜きの同調」、「緊張感の低下」により、社会的手抜きが生まれます。看護業界においては、その成れの果てがお局なのです。
悲しいことですが、お局は成長を目指すのではなく、個人の感情で動きます。
しかし、重要なことはお局単体が悪いのではなく、マネジメントの問題であるという事。
社会的手抜きの原因のほとんどは、自分ではどうにもできず、仕組みで何とかするしかありませんよね。お局もまた、看護業界のマネジメントが生んだ負の遺産なのです。
腐ったリンゴ効果:お局は感染拡大する
お局はお局とつるみます。そして新たなお局が生まれます。
腐ったリンゴ効果とは「集団の利益をないがしろにするような利己的振る舞いをする者がいた場合、その影響が広まり、集団全体を利己的人間の集まりにする可能性がある」
まさにお局ですね。新人を育てて、仕事のできる人間にすることは、自分にとっても集団にとっても利益のあることです。
それを無視して、自分の感情おもむくままに新人を責めて泣かせて嫌味を言う。明らかに利己的振る舞いです。
もちろん新人の中にもやばいやつはいます。でもそれを見極めるには時間が必要ですよね。
その時間も持てないのは、彼女たちに残された時間が少ないからでしょうか…。(笑)
ちなみに、腐ったリンゴは非常に強く、罰を与えても行動は変わらないそうです。なので、腐ったリンゴ(お局)は早めに切り捨てて、腐る前の新鮮なリンゴ(新人)をしっかり育てるべきでしょう。
お局が発生しないためには
ここまで、お局がどうして発生するのかを社会的手抜きを使って解説しました。
では、どのようにしたらお局は発生しないのでしょうか。
個人の努力?人間性?マネジメント?
残念ながらこれは、「マネジメント」の問題です。
フィードバック
1つはフィードバックをすること。
個人が行った仕事による集団への貢献を、言葉や数値でしっかりフィードバックしてあげることでしょう。
貢献を具体的に示すことで、自己効力感を上げます。
「評価可能性」と「努力の不要性」についてはきちんとフィードバックをしてあげることで、対処できます。
つまり、マネジメントをする上層部がしっかりする必要があるという事ですね。
個人レベルでの対処は難しそうです。
ケーラー効果
「自分より能力の高い人を尊敬して、自分の能力の低さで迷惑をかけないように動機付けを高める」ことをケーラー効果といいます。
入職した新人看護師ははじめ、この効果によりパフォーマンスが上がると考えられます。
つまり、お局を発生させないためには、尊敬できる人格を持った能力の高い上司をプリンターや主任として配置することが必要です。
ケーラー効果によって成長し、自分がされたように、後輩にも尊敬されるように頑張ろうという気持ちがわきます。好循環の始まりです。
結論:マネジメントの問題です。
結局のところ、お局が発生するのはマネジメントの問題です。
看護管理は非常に難しいです。マネジメントが得意な人が必ずしも、管理者になるわけではないのです。
Googleなど優秀な企業の職員は生き生きと働いています。看護師は死んだ顔で働いています。この違いは何なのでしょうか?
元々の頭の良さ?仕事の内容が違うから?
答えは分かりませんが、1つだけ言えることは看護師の労働環境は劣悪だという事。
いじめてくるお局がいるというのであれば、職場をすぐにやめるべきです。もっと良い環境が絶対に見つかるはずです。
[kanren postid="275"]今回はパーソナリティについては解説しませんでした、
別の機会があれば、性別やパーソナリティによる社会的手抜きの違いについて解説します。
読んでいただき、ありがとうございました。