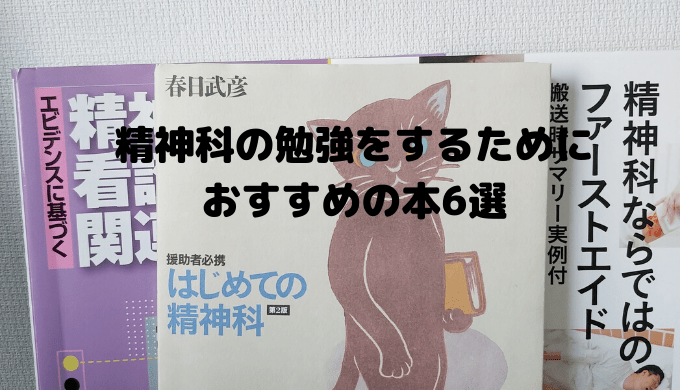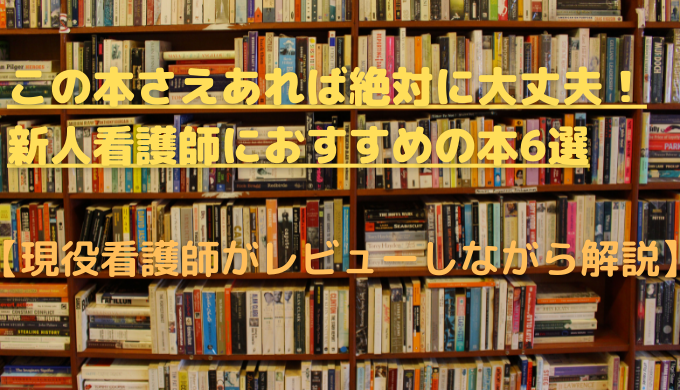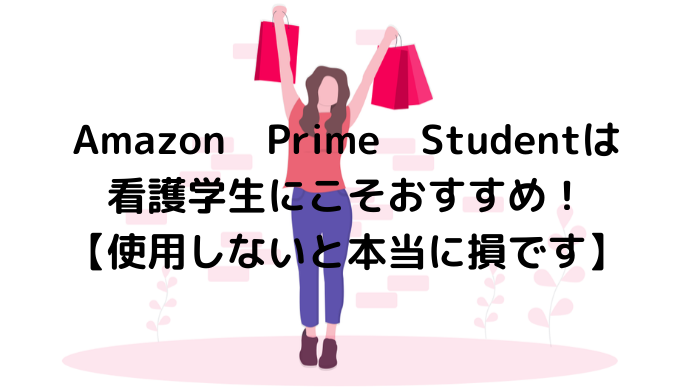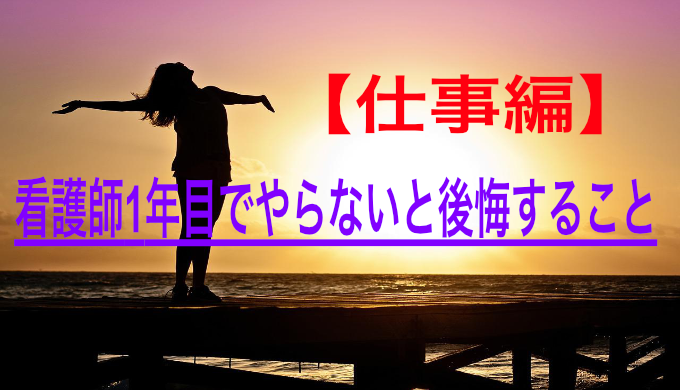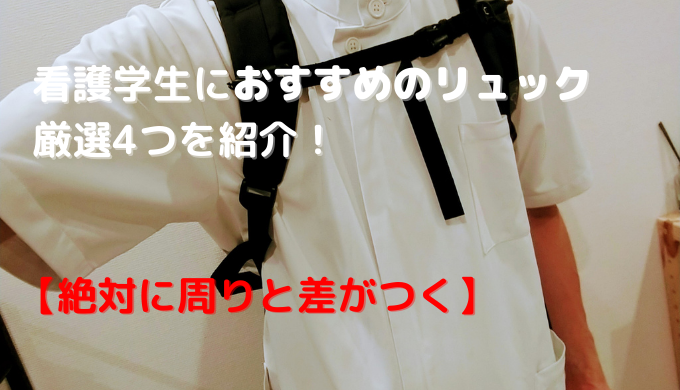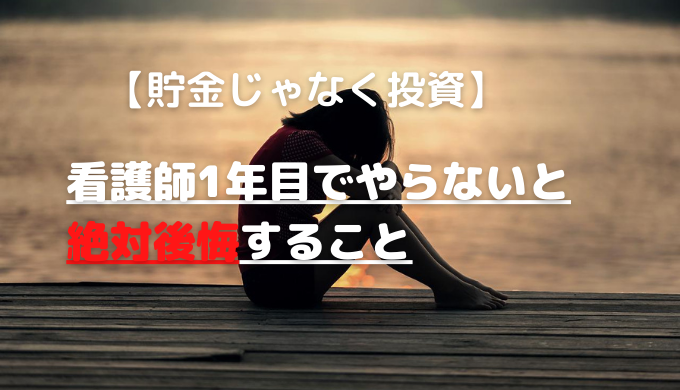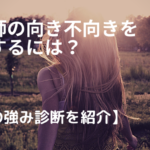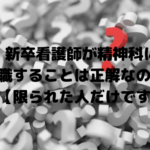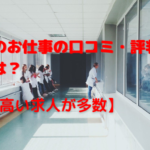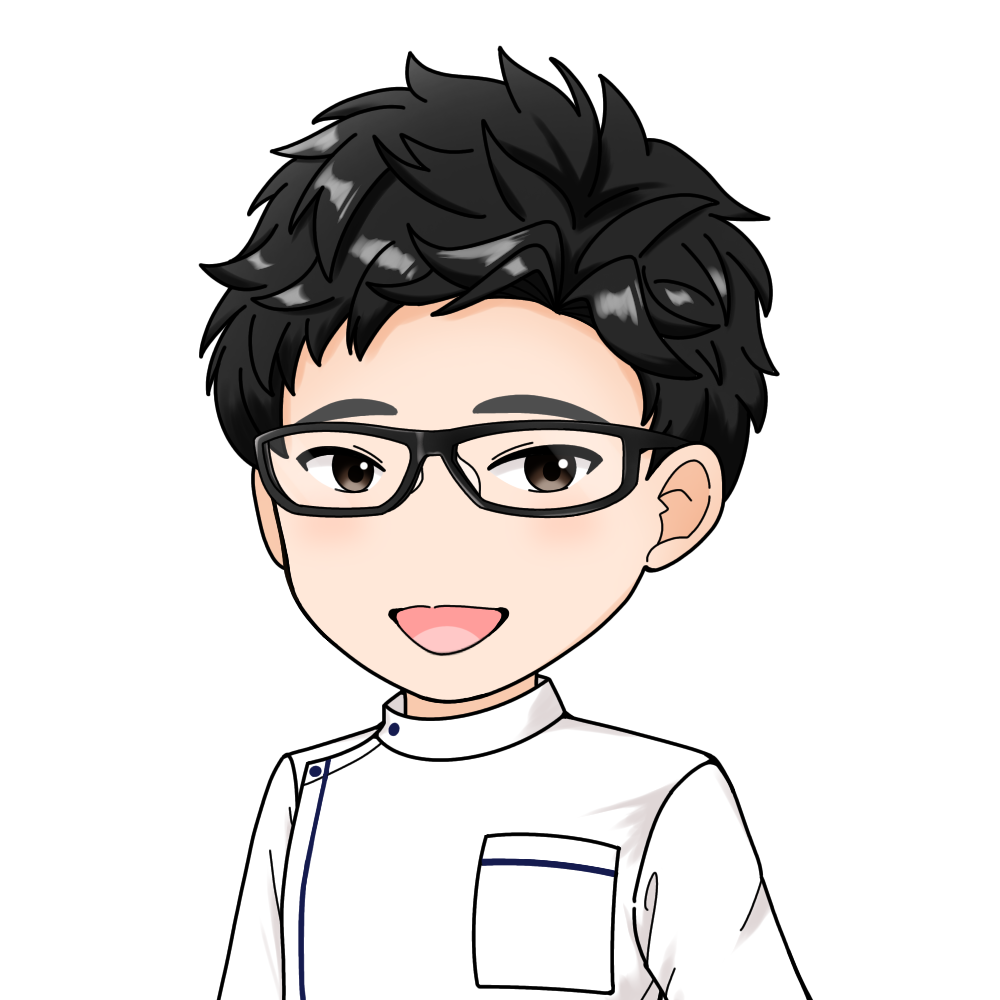行動経済学という言葉を知っていますか?
行動経済学とは「経済学と心理学を統合することで、直感や感情に振り回される合理的でない人間の行動を分析する学問」のこと。
簡単に言うと、「人間がなぜ不合理な行動をとってしまうのかを分析している」分野になります。
今回は行動経済学の中でも有名であり、実際にマーケティングなどで活用されている【フレーミング効果】について解説していきます。
看護師は患者や家族とコミュニケーションをとる場面が多いですよね。
例えば、手術の選択、術後の退院指導、など中には重要な選択の場面に立ち会う事も多く、どう伝えるべきか悩むことがあります。
実は【フレーミング効果】を知ることで、「他人を意図的に誘導」することができるようになります。
なぜうまく伝わらないのだろう。どう伝えたらいいのだろう?そんな場面に立ち会ったとき、【フレーミング効果】が役に立ちます。実生活や医療現場においてぜひ活用してください。
✔記事の信頼性
・現役の精神科看護師
・スーパー救急病棟勤務
目次
フレーミング効果とは?
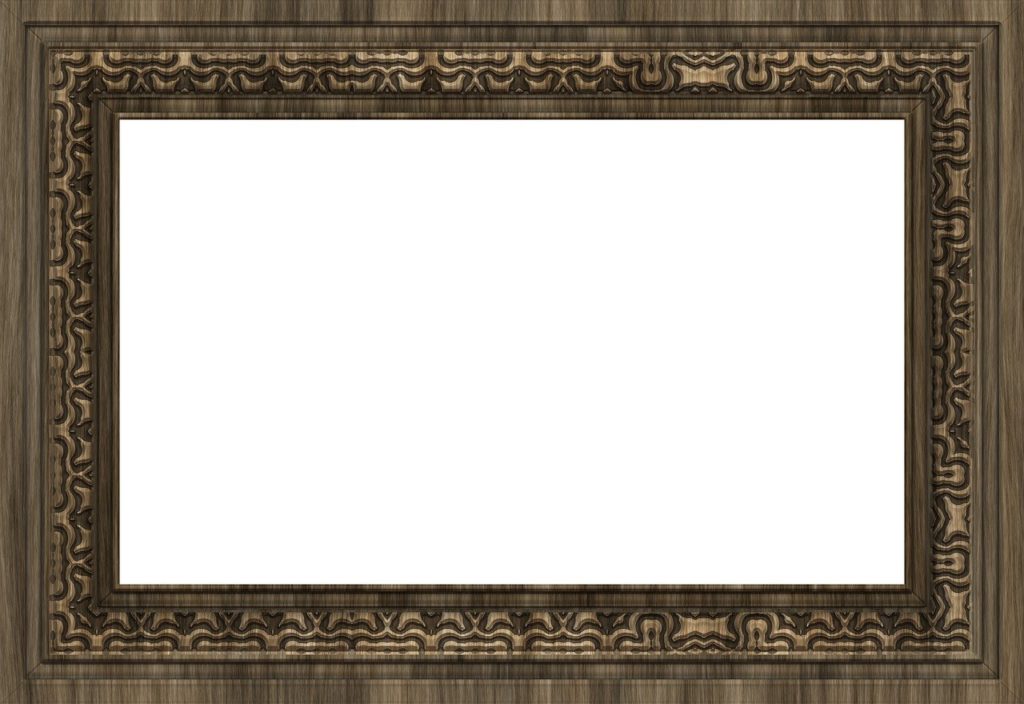
フレーミング効果とは、「人がある選択をするとき、その絶対評価ではなく、自分の基準に当てはめて別の判断をしている可能性がある」こと。
これだと少し分かりづらいので、簡単に説明すると
「伝える内容は同じでも、表現の仕方で印象を変えることができる」効果のことです。
分かりづらいので、実際に行われた実験と例を紹介していきましょう。
フレーミング効果の実験
行動経済学の代表作であり、名著「ファスト&スロー」では、このような研究が紹介されています。
アジアで発生した怖い病気で、600人の死者が出ると予測された。この病気から一般市民の健康を守るために、次の2つの治療法から1つを選ばなければならない。
A:この治療法では、200人の命は助かる
B:この治療法では、600人の3分の1が助かるが、残りの3分の2は助からない。
アジアで発生した病気で、600人の死者がでると予測された。次の治療法から1つ選ばなければならない。
C:この治療法では400人の命が確実に助からない
D:この治療法では600人が死ぬ確率が3分の2。死者が1人も出ない確率が3分の1である
最初の質問では多くの人がAを選択。2つ目の質問では多くの人がDを選びました。
しかし、よく見てみるとどの選択肢も結果は同じです。(200人が助かる結果)
つまり、私たちは確実に救われるという設定に対して、「安心」し、逆に確実に死ぬという設定は「嫌う」ようなのです。
この研究で何が言いたいかというと、「表現の仕方によって、相手の選択に対して影響を与えることができる」、という事です。
フレーミング効果の例
日常で使われている例を紹介していきましょう。
患者満足度調査のアンケート結果の表現の仕方
・満足度90%
・不満度10%
転職サービスやジムの広告で、満足度調査90%!というのよく目にしませんか?
その数字だけを見ると、このサービスは信頼できそうだな、と感じますよね。では、これを不満度10%と表現するとどうでしょうか。なんとなく嫌な感じでサービスを受けたくなくなりますよね。
このように、同じ事実でも相手に対してどのように表現するかで、与える印象が変わるのです。
もう一つの例を見てみましょう。
有名な某栄養ドリンクのタウリンの量
・タウリン3g含有
・タウリン3000㎎含有
栄養ドリンクの成分表示をよくよく見てみると、1000㎎単位で表示されていませんか?
入っている量としては同じでも、3gを3000㎎と書いただけで沢山入っているような気がしますよね。コンビニやスーパーに売っている商品の栄養価の含有量を、まじまじと見て考える人なんてほとんどいません。
つまり、ぱっと見ただけで「沢山入っているな」と思わせることができるように工夫しているのです。
商品開発をしているマーケティング部門は、このような心理を理解してあなたに消費をさせようとしています。
医療現場でのフレーミング効果の例

では医療現場で活用するにはどのようなフレーミングがあるでしょうか。
がんの手術をする予定の方に対しての説明
・術後1か月の生存率は90%
・術後1か月の死亡率は10%
誰もが「死亡」というマイナス表現を嫌うので、前者の「生存率」を示した方が安心できます。
KAIは精神科に勤めていますが、内服の継続って永遠の課題なんですよね。なので下記のように説明します。
〇 抗精神病薬を内服している人の80%が通常通りの生活が送れます。(数字は適当です)
× 抗精神病薬を内服していても再発する人がいます。
あとは、訪問看護の説明をするときにメリットを示すような表現をします。
〇 訪問看護が導入されていると、60%の方が再入院しません。
× 訪問看護を導入しても、40%の方が再入院してしまいます。
できる限り、プラスに感じるような表現を使います。
損失に注目させないよう、利益に着目した説明をするということがポイントですね。
人間の損失回避性については有名な「リスペクト理論」がありますが、それはまた別記事で解説します。
臓器提供のフレーミング効果

臓器提供の意思表示をするドナーカードをご存じですか?
ここにも実は非常に大きなフレームが使用されているのです。
臓器提供への同意率
オーストラリア ほぼ100%
ドイツ 12%
スウェーデン 86%
デンマーク 4%
隣国であり文化的に似通った国なのに、同意率にこれだけの差があります。これはどうしてでしょうか?
実は質問形式、つまりフレーミング効果が原因なのです。
どういうことかというと、
同意率が高い国では、提供したくない人は所定の欄に✔マークを入れなければなりません。✔をしないと同意したという事になります。(オプトアウト方式)
一方、同意率の低い国では、提供したい人が所定の欄に✔マークを入れなければなりません。(オプトイン方式)
たったこれだけの違いです。すごいですよね?
臓器提供に対して強い反対を示す人は同意を拒みますが、たいていの人はそんなに真剣に考えていないんですよね。その結果、最初から同意前提の質問にすれば、多くの人が拒否をしないという形に落ち着くのです。
ちなみに、日本は自分で選択できる方式を取っていて、同意率はなんと12.6%とかなり低いことが分かります。
医療現場でフレーミング効果を生かす場合
これを看護やマネジメントに生かすことを考えてみましょう。
よくある悩みが、研修の参加率が低い。必要な書類の提出が遅い。などではないでしょうか。
強引ですが、研修の参加率について伸び悩んでいるときに、基本は強制参加で拒否が可能という設定にすれば、参加率が上昇することが予測されます。
また、提出物が遅い場合は、「現在何%の人が提出できています。」というポジティブな表現をしたものを掲示しましょう。ルールを守っている人が沢山いる!という事を示してあげるのです。
ポジティブな集団の一部であると認識させることでよい行動を継続させることができるかもしれません。
まとめ
・フレーミング効果では、損失より利益になる言葉を使って表現するべきである。
・数字を示すときは大きな方で示す
・参加率を上げたいときは任意参加ではなく、強制参加前提で拒否ができる設定にする
看護実践の際にぜひ活用してみてください。関係者、患者、家族に対する印象をより良いものにすることができるはずです。